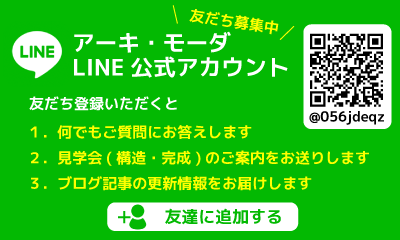代表の鈴木です。
今日はメンテナンスコストから考える家づくり「外壁編」というタイトルでお話ししたいと思います。
メンテナンスに対する考え方もいくつかあって、とにかくメンテナンスサイクルを伸ばすことを優先するのか、それともメンテナンス時のコストを抑えることを優先するのかで家づくりの方向性も変わってきます。

着目すべきはメンテナンスサイクルか、それともメンテナンスコストか!?
住宅業界に約30年身を置いて、多くの住宅を建築し多くの住宅をメンテナンスしてきた経験から言うと、私なら「メンテナンス時のコストを抑えることを優先した家づくり」をおすすめしたいと思っております。
しかしながら、多くのお客様は家のメンテナンスそのものが煩わしいと考えているようで、それもあって一般的に多くの住宅会社、及びハウスメーカーは「メンテナンスサイクルを伸ばす提案」が主流となっているのも現状です。
それには住宅会社やハウスメーカーにとっても都合がいい事情があります。
「メンテナンスサイクルを伸ばす提案→高耐久商材の提案→高価格商材の選択→利益率が高いく儲かる」という、商売の原理原則に沿っているからです。
もちろんメンテナンスサイクルを伸ばすことも大事ですが、それには費用対効果とのバランス検証がとても大事かと思います。
それぞれ解説をしていきたいと思いますが、まず家を建てた後に一番最初にかかるメンテナンスで覚悟しなければならない大きな出費を伴うことはなんでしょうか!?
一番コストがかかるメンテナンスとは!?
ずばり!それは建て替えです。
「えっ!、建て替えなんて何十年も先だよ!」
ほほ100%の方はそう言うでしょう。
ではこう考えてみてください。
例えば、本日待ちに待った新しい夢のマイホームのお引渡しを受けたとします。 そしてなんと次の日に大地震が発生し、2016年に発生した熊本地震のような繰り返し震度7の地震に見舞われました! 幸いにも新しい家は倒壊することなく、家族の命も守ってくれましたが、建物は大きな損傷を受け住み続けけることは難しそうです。 解体して建て直すか、そのまま土地の価値だけで売ってしまうか…
いかがですか⁉︎
これは有り得ない空想の世界の話でしょうか!?
大袈裟な話だと思うならそれでも結構です。
- これから支払いが始まる住宅ローンはどうなると思いますか⁉︎
- 住宅会社の保証期間内だから大丈夫ですか⁉︎
- 地震保険に入っているから大丈夫ですか⁉︎
あなたの思惑は全て大きく外れます。
メンテナンスサイクルも意識せず選んだどんなに安い外壁や屋根材も、たった1日で劣化することはありません。
今の商材ならば、少なくとも10年から15年は保つでしょう。
でも、大地震やモンスター級の台風は一瞬にして建物の寿命を奪う可能性があります。
「新築だから大丈夫!」という問題ではありませんよね。
なので一番最初に覚悟しなければならないメンテナンスは建て替えなのです。
【今日引渡しを受けて、明日マイホームを失う!?】
このような悲劇を避けるために現時点で最良の対策は、構造計算(許容応力度計算)をした建物を計画することです。
これが実現できて初めて10年後、20年後のメンテナンスを考える意味が出てきます。
なので、まずメンテナンスコストから考える家づくりの第一歩は、構造計算(許容応力度計算)をして耐震等級3、耐風等級2を取得した建物を計画することから始まります。
関連記事:木造の構造計算って!?【日本一わかりやすい木造の構造計算の解説】
大前提の話をした上で、次にみなさんが気になる10年後、20年後のメンテナンスの話に戻りたいと思います。
メンテナンス時にかかるメンテナンスコストに着目すべき!
まず、なぜ私がメンテナンスサイクルよりもメンテナンス時のコスト優先で考えた方が良いと思うかをお伝えしたいと思います。
「メンテナンスフリー」とは大変魅力的言葉ですが、まず大前提としてメンテナンスフリーの仕上げ材は存在しないと言うことを認識していただきたいと思います。
どんな商材や仕上げ材を選んでも伸ばせるメンテナンスサイクルは20年から30年が限界です。
約10年の幅を持たせて表現したのは、地域の気候特性や立地条件、建物の形状によって大きく変動するからです。
外壁のメンテナンスサイクルは素材ではなく軒の出で決まる!
建物のメンテナンスというと多くの方は外壁に着目すると思いますが、外壁のメンテナンスを気にするので有れば何の素材を選ぶかよりも、とにかく屋根の軒の出にこだわるべきです。
外壁の劣化は、風雨にさらされる環境ももちろんですが、それよりも紫外線による影響が非常に大きいのです。
我々人間でも、肌の劣化を防ぐために紫外線対策として日傘をさして紫外線をさけるように、建物にもしっかり傘をかけるべきです。
これは設計計画の問題ですね!
ところが立地条件により、なかなか十分な軒の出を計画できない場合が少なくありません。
建物どうしが隣接し、限られた土地に厳しい法規制の中で計画せざるを得ない都市部の住宅は、満足に軒の出を計画できないケースがほとんどです。
そんな時はなるべく外壁の総面積を抑える設計計画を行いつつ、外壁の素材選びが重要になってきます。
タイルは最強の外壁材か!?
そこで良く話に上がるのは、メンテナンスを考慮して外壁にタイル張りを選択したいという要望です。
もちろん間違いではありません。
タイルの耐久性は他の外壁材と比べても圧倒的に高いですし、重厚感やデザイン性も非常に高く、満足感も得られるとても優れた素材です。
その反面、非常に高価格であることが採用にあたってネックになっています。
「高くてもメンテナンスサイクルが伸びるのであれば結果的にお得!」という営業トークを良く耳にすると思いますが、本当でしょうか!?
私はここに疑問を感じるので、メンテナンスサイクル重視の素材選びにはやや否定的なのです。
タイル張りの外壁も生涯全くメンテナンスフリーとなるわけではありません。
通常外壁は、見た目の劣化や汚れ具合から「そろそろメンテナンスが必要かな!?」と判断されますが、タイル張りの場合は見た目でそのような印象を与えてくれないケースがほとんどなので、ある一定期間が経過した時点で必ず自発的なチェックが必要となります。
マンションなどが行う大規模修繕の要領で、建物全体に足場をかけてタイルの付着状態を確認したり、目地の欠落状態を確認することが必要となります。
見た目で劣化具合が分かりづらいのが外壁タイル張りのデメリットで、劣化具合が目に見えるまで放っておくと、今度はタイルの脱落による思わぬ事故を招くこともあります。
また完全に劣化した状態での再施工は、とてつもない時間と費用がかかります。
仮に30年メンテナンスが不要だとしても、やっと住宅ローンが完済する頃にまた数百万のメンテナンス費用がかかるというのは大きな負担になるはずです。
このように、たとえ高耐久の仕上げ材であるタイル貼りの外壁でさえ、ずっと何もしないで放っておけるわけではなく、定期的に足場をかけて状況確認というメンテナンスが必要なのです。
足場を掛けるだけでも数十万円かかりますのでタイルの外壁にしたからといってメンテナンスコストがかからないとは言えないのです。
どんな仕上げ材でも結局メンテナンスが必要であれば、メンテナンス時にコストがかからない仕上げ材に着目すべきと考えるのは以上の理由からで、ここからは特に外壁材に焦点をあてて話を進めていきたいと思います。
■関連記事:注文住宅でオススメの外壁材 | 意外な選択とは
メンテナンス時のコストから考える外壁材
おすすめは「木製のサイディング」
まず、外壁のメンテナンス時に一番コストがかからない仕上げ材は「木製のサイディング」です。
ちょっと意外かもしれませんが本当です。
主に「木製のサイディング」のメンテナンスは浸透性のオイル系塗料を塗布することなのですが、とてもローテクで誰でも塗ることができます。
だからと言って素人が作業することではありませんが、プロに頼んでも費用も安く塗料もホームセンターでも手に入るほど入手が簡単です。
作業にあたってはそれほど音が出ることもありませんし作業工程もシンプルで作業日数も短く済むのが特徴です。
もし傷んでいる箇所があれば部分補修が可能です。
木はこれから先も入手困難になることはまず考えにくく、特殊な業者ではなくても大工さんで補修が可能な点も費用的な視点で考えても魅力的と言えます。
木の廃材処分費も他の素材と比べて圧倒的に安いことも隠れたメリットの一つです。
「木は腐ってしまうので耐久性がないのでは?」
と心配される方も多いとは思いますが、「木製のサイディング」の耐久性は意外と高く、定期的なメンテナンスを施せばかなり長寿命化させることが可能です。
デメリットとしては、準防火地域や防火地域で計画される場合は使用できる「木製のサイディング」がかなり限定され費用が高いということです。
また紫外線による劣化が他の外壁材よりも早いので、特に南面に計画するとメンテナンスサイクルを早めます。
ガルバリウム鋼板製の金属サイディングもおすすめ
次にメンテナンスコストがかからない外壁材は「ガルバリウム鋼板製の金属サイディング」です。
屋根にも使われる素材ですので、耐久性の高さは折り紙付でメンテナンスサイクルも長く優れものの素材です。
外壁材の中ではタイルの次に耐久性が高い素材と言えます。
非常に軽い素材なので、建物にも負担をかけません。
メンテナンス時も特別な下地処理が不要で表面の塗装だけで済みます。
デメリットとしては、衝撃に弱く凹みや傷がつきやすいと言うことです。
窯業系のサイディングは万能なのか?
さて、世の中で一番多く使われている「窯業系のサイディング」はどうでしょうか?
年々プリント技術が向上し、様々な色柄バリエーションが存在しています。
光触媒や親水性加工によって汚れがつきにくい、あるいは雨水で汚れが洗い流されるという商品も充実しています。
またサイディングの耐久性を語る上で一番の弱点となるコーキングの劣化についても、その対策としてコーキングレス仕様のサイディングも登場しています。
高価格帯のサイディングを使用すれば、以前と比べメンテナンスサイクルを伸ばすことは可能ですが、来るべきメンテナンス時は厄介な問題があります。
まずサイディングのメンテナンスの基本は表面に塗装をすることですが、再塗装時に既存の色柄に戻すことは不可能で、全て単色柄になってしまいます。
また部分補修で一部張り替えをしたいときなどに何年も前の同じ商品を手に入れることはほぼ不可能なので、継ぎ接ぎの色柄で我慢するか、ある程度の面で区切って張り替えるかの選択になってしまいます。
工事も専門の外壁業者が必要となりますし、既存サイディングの処分費は木や金属と比べても高額となります。
作業時の音も大きく、近隣に気を使いながらある程度の日数を過ごさなければなりません。
このように工業製品=サイディングのデメリットはメンテナンス時に現れます。
歴史があるモルタル下地に塗り壁の外壁材は!?
サイディングよりも古くから存在し、今なお人気の仕上げ方である「モルタル下地に塗り壁の外壁材」はどうでしょうか?
塗り壁のメンテナンスもサイディング同様に表面に新たに塗り重ねるのが一般的ですが、サイディングと違うのは元の色柄を再現することが可能ですし、違った色柄に変えることも可能な点にあります。
またメンテナンスにおいて余程のことがない限り、下地のモルタルごと撤去しなければならないケースはありませんので表面の仕上げだけで済みます。
サイディングの張り替えと比べれはかかるコストははるかに安くあがるのはメリットです。
塗り壁のメンテナンス時のデメリットは、サイディング同様に部分補修が難しい点です。
経年劣化している周りとは色柄を合わせることはなかなかできませんし、年々高齢化している左官職人のことを考えると、いつまでこの仕上げが維持していけるのかも心配事の一つです。
まとめ
代表的な外壁の仕上げごとにメンテナンスの視点で解説してきましたが、最終的には採用時のイニシャルコストとメンテナンス時のコストのバランスを見ていかなければなりません。
もちろん、好き嫌いもあることでしょう!
私なら「木製のサイディング」と「ガルバリウム鋼板製の金属サイディング」の組み合わせをお勧めしたいところです。
「窯業系サイディング」や「モルタル下地+塗り壁の仕上げ」よりも価格は上がりますが、メンテナンス時のコストは比較的安価に抑えることができますし、木と金属という取り合わせが高いデザイン性も両立させてくれます。
傷や凹みに弱い「ガルバリウム鋼板製の金属サイディング」は上階部分(手の届かない範囲)に使用することでそのリスクは軽減されますし、「木製のサイディング」は脚立で届く範囲の高さに抑えた計画によって足場不要でメンテナンスが可能です。
みなさんが関心のあるメンテナンスサイクルについては先にも話しましたが、素材選び以上に建物のデザインや設計計画によって影響を受けます。
まずは外壁に負担のかからない設計計画を実現させて、足らない要素を素材選びで補う考え方が最良かと思います。
逆を言えば、建物のデザインや設計計画において十分配慮ができるのであれば、外壁材選びにそれほど神経質になることはないと言えます。
最後に外壁材の色について1つだけアドバイスをさせていただきます。
【真っ白に近い白】で仕上げられた外壁は、極端にメンテナンスサイクルを早めますのでご注意を!
それではまた。
■こちらの記事もおすすめです
関連記事:SE構法とは何?【日本一わかりやすい「SE構法」の解説】
2020.06.27
【アーキ・モーダ LINE公式アカウント】
アーキ・モーダのLINE公式アカウントでは、
「家づくりの質問になんでも答えます!」をやっております。
【YouTubeも始めました!】
是非、高評価、チャンネル登録お願いいたします!
アーキ・モーダのLINE公式アカウントでは、「家づくりの質問になんでも答えます!」をやっております。